能登半島視察報告
- サイト管理者
- 2024年8月28日
- 読了時間: 11分
更新日:2024年12月24日
2024年8月26日から28日、能登半島地震について、現地視察及び調査を行いました。
以下、視察のご報告をいたします。
場所 | 石川県女性センター |
目的 | 被災地における女性の声を聴き、埼玉県の参考とする |
概要 | 石川県庁内では春以降、復興専門の部署が創設され、検証事業が行われている。今回県庁自体への訪問は叶わなかったが、発災後、女性センターで行ってきた支援について伺うことができた。各種女性団体が、炊き出しや支援物資の配布を行ってきた活動状況や、女性センターで行われたイベント(2月22日)からも、衣類や化粧品の無料配布とともに、お悩み相談が重要な支援であることが分かる。傾聴ボランティアだけではなく、住まいの相談、仕事の相談、弁護士相談など専門窓口を設けていた。 金沢は震度5強であり、震度7であった輪島や七尾などとは距離的にも心理的にも少し距離がある。避難所に関する相談窓口も県庁で一元化され、金沢市内の避難所も今月末ですべて閉まるとのことであった。 |
成果 | 危機管理部門における女性職員の割合は平成19年能登半島地震以降、徐々に増えてきているとのことであり、防災における女性視点の重要性が経験を通じて高められていることが分かった。例えば生理用品に関しても、男性だけでは感覚のずれが生じてしまう現実が今回もあったと伺い、防災における男女共同参画をより的確に埼玉県でも進めていく必要がある。女性職員比率など更に高めていけるよう議会を通じて求めていく。 |
写真 |  |
場所 | 石川県災害ボランティア協会 |
目的 | 被災地支援の現状を知り、埼玉県で災害が起きた時の想定をするため |
概要 | 輪島市でのボランティア活動の状況を伺った。仮設住宅の見回りを金沢大学、北陸学院大学、東北学院大学、桜美林大学等の大学生ボランティアと共に行い、様々なイベントも企画している。仮設住宅にこもり、自殺などが増えてくるのはこれから。少しでも前向きな気持ちを持ってもらう、人と交流することで孤独孤立を防いでいきたいとの狙いから、今後は高齢女性には冬の手仕事としてミサンガを作成してもらい、朝市組合と組んで、組合のキャラクターである「あさいっちゃん」をつけて大学の文化祭や出張朝市などで販売する予定。難しいのは受援力のない方々で、漁師であったが仕事を失ってしまったような高齢男性がこもりがちになっている。 公費解体は現在2年待ち。自費解体をしてから補助金を受けるケースも認められるが、全額補助を受けられるかわからないと心配する声も多いとのこと。今は県外の業者でも認められるようになったが、最初は様々な括りがあり復興が遅れた。現在でも建築・土木・設計など提出しなければならない書類が多すぎて煩雑であり被災者は苦労している。 被災すると、元々家庭内にあったトラブルが表面化し、家族間の相談が増える。離婚する方も多く、また、子ども夫婦を頼り同居してみたが結局、避難所に帰ってきてしまうケースも多い。 自宅で避難生活を送ることが一番ストレスは少ない。避難所は鳥かごの鳥と同じで自由が奪われ、プライバシーもなくなり、人権が奪われている状態と言える。自宅避難できる準備を徹底すべきであるし、デイサービス等介護などの社会資源も早く復活させ、少しでも早く日常を取り戻すことができるようにすべきである。 |
成果 | お盆に行った三夜祭りは観光客も来て盛況だったとのことで、改めて平時からの顔の見える関係性が大切であることを感じた。日常生活を取り戻すこと、希望が持てるような何かがあること、そうした生きるために必要な社会生活を整えていくことは政治の役割なので、平時からの備蓄の在り方も含め、防災意識の啓発を行い、想定される事態を整理しておく等、埼玉県の防災力の向上に学びを生かしていく。 |
写真 |  |
場所 | 穴水町役場 |
目的 | 震度6強を経験した被災地がどのように復興の道を歩んでいるのか、課題や教訓を知り、埼玉県への学びとするため |
概要 | 穴水の被害状況と復旧状態について、道路、電気、水道、下水道、通信それぞれがいつ復旧したのか。被害家屋数や、避難所の開設状況、公費解体の進捗状況、仮設住宅の入居状態について資料を基にご説明いただく。 電気もケーブルテレビも使えないなか衛星電話であるスターリンクが有用であったとのこと。避難所は町内で58か所約3800名が入所していたが、8月12日に全避難所が閉鎖された。1.5次避難所としていしかわ総合スポーツセンター、2次避難所として温泉旅館等が受け入れてくれたが、現在は全員退所している。公費解体は住家は申請件数700棟のうち34%が解体完了している。来年度中には完了したい。仮設住宅は517世帯1053名が入居している。 また、役場として各課がどんな震災対応をしたのか、それぞれの課題、復興計画についても伺った。本部班として環境安全課、総務課、議会事務局が割り当てられた。他には、食料物資班は観光交流課、総務課。被災世帯調査班は税務課。住民生活班は環境安全課、住民福祉課、会計課。要援護者支援班は住民福祉課、子育て健康課。土木農林水産班は地域整備課。上下水道班は上下水道課。医療班は公立穴水総合病院。文教対策班は教育委員会事務局といった分け方である。
①職員の配備 発災日が元旦であったため、職員の登庁が困難であり、全職員が配備されたのは発災から10日後であった。 ②通信インフラの脆弱性 電話やネット、テレビの不通により情報の収集・発信ができなかったうえに、道路の損壊により復旧作業が難航した。通信関係が全復旧したのは発災から7日後であった。 ③避難所の開設 閉庁日、休館日であったため公共施設が施錠されており避難所開設が遅れた。暖房器具の不足、災害時用自家発電機に不具合もあった ④受援体制の準備不足 国の応急対策職員派遣制度に基づく総括支援、対口支援の受け入れ体制の知識と経験不足により、戸惑いがあった。普段100人の職員がいるが、国のリエゾン、対口支援先であった静岡県(リーダー県)、奈良県、栃木県、福岡県から25人が来てくれたが、宿泊場所の確保等も考えねばならなかった。道路の設計関係の支援は足りていなかったと感じている。
避難所等への必要供給量と支援量との調整が困難であった。奥能登への道路が通じていなかったため、穴水に以北の分の食料も置いていかれており、北から小さい車で穴水に取りに来る状況であった。
帰省者等の増加で災害備蓄品の不足や配送職員、配送車両の不足、また、賞味期限問題もあり、物資が少なかった。
断水等で衛生面が悪化することで健康被害がおきる。長期避難所生活者への健康管理と精神的なサポートが必要であった。
避難所利用者の名簿作成と情報共有の必要性。車中泊など避難所以外の場所での避難者の把握が困難であった。
町立穴水小学校の被害規模が大きく教育活動の実施が困難になった。2学期から仮設校舎で授業は実施予定だが、指定避難所としての機能が低下していた。
震災・教育環境の変化による心身的な負担への対応、避難所生活でインスタント、レトルト食品の長期的な摂取による栄養バランスの欠如。
①医療提供体制の機能低下 公立穴水総合病院では施設の損傷、看護師の離職で医療がひっ迫していた。
下水道の復旧が遅れたことで、浴室・トイレが長期間使用不可であった。また、施設内で患者や入所者と避難者が混在していた。
復興プランは、地区懇談会を各地で開きながら穴水高校の生徒にも入ってもらい、若者や移住者の意見も取り入れている。町としての大きな課題は人口減少であり、若い人ほど町を出ている。広い土地がないので、大きな企業を誘致するわけにもいかず、町内の仕事は、第一次産業、建設業が中心になる。給食費、医療費、保育費の無償化等で子育て環境の整備も進めているが、流出に歯止めがかからない。 |
成果 | 被災状況により各自の状況が異なっているので、一人一人に寄り添う姿勢が大切だと痛感した。また、感染症を考えても家は大事なので、仮設住宅を早く建ててもらうことが重要だと指摘したうえで、宮崎副町長が発災前にやっておけば良かったこととして挙げられたのが、各地でおこってきた災害報告書を読んでおくことだった。発災して始めて読むのでは遅い。穴水町は既に今回の地震での対応をまとめた資料を作成されており、復旧の早さはトップに立つ方の決断力が大切であることがよくわかった。埼玉県でも、前線に立つ各市町村を県としてしっかりサポートできるよう、県の役割を再考すべきと考える。 |
写真 |  |
場所 | NPO法人レスキューストックヤード |
目的 | ボランティアセンターを運営するNPO法人の活動から被災者支援のあり方を埼玉県の参考とする |
概要 | 【レスキューストックヤードと穴水町】 2007年の能登地震の時に穴水町に支援に入っていたので、元々社会福祉協議会と関係性ができていた。今回も発災後すぐに社協と連絡を取り、1月3日には現地入りをした。断水と停電が長く、地理的要因に加え行政職員も多数被災されていたこともあり、支援が入りにくかった。 当初学童施設の避難所にいたが、蓄電池で充電し、電池でランタンを灯し、トイレは凝固剤、手洗いはペットボトルの水と手指消毒、寒さ対策はホッカイロであった。食料支援とお風呂支援が遅かった。 穴水は4つの地区(穴水・住吉・兜・諸橋)に分かれており、諸橋地区は穴水から車で40分ほどかかる山間部で10軒のうち7軒は高齢者が住んでいる高齢過疎エリアである。移動手段がなく、買い物は移動販売車にお世話になっているが、牛乳1本400円とのこと。
【住まいの問題】 仮設住宅は20か所に532戸できており、集会所は50人に1つ、談話室は30人に1つの割合で併設されている。被害家屋の判定は6区分に分かれているが、仮設に入れるのは自宅が「半壊」以上の方となっている。よって、「準半壊」の方は一部半壊していても自宅にいるしかない。今回、石川県は「準半壊」でも自宅が修理中は仮設に入れるようになっているがどの判定になるかで救済措置に大きな差がでる。応急修理制度による補助は「準半壊」30万円と「半壊」60万円となっている。 判定が不服であった場合、納得のいくまで判定をやり直してもらうことができる。行政は1回目は家を外からしか目視しないで判定する。再申請すると、2回目は中を見てもらえるので、被災直後の家の中の写真を必ず撮っておいた方がよい。ただ、再申請して判定が下がる可能性もあり、多くの方はそれを心配して再申請に踏み切れない。判定は点数制となっており、建築士と共に被災者宅を回って相談を受けているが、今何点で判定されているのか被災者に明かされていないことは問題である。
【行政・NPO・社協の連携について】 国の「被災高齢者等把握事業」と「見守り支援事業」は双子の事業で、これにより人件費や交通費への補助が出るようになった。穴水町は、社会福祉協議会とNPO団体、行政の3者連携がうまく機能している。子育て支援課が復興担当となり、社会福祉協議会は支え合いボランティアセンターを運営し、レスキューストックヤード他NPO団体が支援に当たる。 1月末から2月は避難所だけでなく被災者宅を訪問し、継続支援が必要な方をピックアップした。5月以降は子育て健康課・NPO・社協・穴水総合病院によるケース会議を2週間に1度開いている。私が訪れた8月末は段階としてはまだ災害ケースマネジメントより一段手前だが、一人一人について家族機能があるのか、介護保険事業者やNPO団体等の社会的地域資源が全くないなか、使える公的制度があるのか、お困り事など何を喋っていたのかまで細かく情報をおさえて共有している。グレーゾーンにいる方が非常に多く、彼らがレッドゾーンにいかないように何ができるのか常に考えているとのことであった。 これからメンタル的なことや災害関連死が増えていく局面。特に男性はひきこもりがちになり、レクリエーションがなくなる「生活不活発」の状態になり、DVやアルコールも増えていく。東日本大震災の時にレスキューストックヤードが七里ガ浜に支援に入った時は10年間活動した。ボランティアで来る方々には細く長く支援を続けて欲しいとのことであった。一方、県を超えた広域避難をした場合、避難していった方々の名簿がないため足跡を追えないという課題もあるとのことであった。 |
成果 | 法に則って公平に支援があっても、どうしてもそのセーフティーネットからこぼれ落ちる人がいる、との言葉が印象的であった。例えば、避難所における発達障害児や認知症の方などは福祉避難所に繋げた方が良かっただろうし、被災後長期間経っても避難所から出られない方々がいる。こうした福祉に繋げた方がいい方々への対処が確立していないとの声は、本県での避難所運営対策にも反映すべきである。 また、行政の役割として、有事にしっかり活動できるNPO団体、社協との連携を平時から深めておくことの必要性を感じた。本県では埼玉版FEMAを行っているが、役割ごとに普段からの訓練活動を共にやることをぜひ進めるべきである。 |
写真 |  |
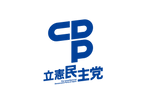


コメント