地方創生・行財政改革特別委員会
- サイト管理者
- 2024年12月18日
- 読了時間: 4分
更新日:2025年1月30日

18日は特別委員会が開かれ、今回は「情報技術の活用とDXの推進について」審議しました。県のDXは大野知事肝入りで進められており、第一段階のデジタイゼーションではペーパーレスや音声認識AIで議事録を作成するなど県庁内部でのDXの土台を作り、そして、現在は第2段階のデジタライゼーションの段階です。デジタルで仕事のやり方を改革するとのことで、ノーコードツールや生成AIを全職員に配布し、業務効率を高め、県民サービスの向上につなげることを目的としています。そして、最終段階はDXで新たな価値やサービス創出をすることを目指しています。
私はDXに関して以下の3点について質疑しました。
質問1⃣
野本Q. RPAで8710時間、生成AIで3123時間が削減され作業の自動化・省力化がすすんだとあるが、この数字はどうやって出しているのか?また、「生み出した時間を県民サービス向上に活用」とあるが、具体的にはどのようなことか?
県A. RPAについては、手作業の自動化ということで、例えば職員に支払う手当を計算するときに、今まで手作業で1件2分だったものが1分になれば1件当たり1分省略できる。これに年間の処理件数をかけて、それぞれの業務を足し上げて算出している。
音声認識AIのほうは、いろいろ調べた結果、庁内の会議で活用すると大体平均2.6時間程度削減効果があるということで、これに年間処理数をかけまして算出している。
それから実際に生み出した時間をどう活用しているかということについては、事例の一つとして、例えば県が講演会をしたときに、これまでは当然講演会を見た人しか中身が分からなかったが、それを音声認識AIですぐに文字起こしをして、ホームページに掲載することで、講演に参加されなかった方も概要が分かるようなったといった事例がある。
野本Q. この間の県民満足度調査で、DXについて「全く知らない」、「あまり知らない」という割合が85%で、かつ望んでいるのは行政手続や公共サービスの利便性向上を74%の方が望んでいる。DXを進める目的やゴールが、県民にもっと共有されていかないと、理解が進んでいかないのではないか。まだDXの良さが県民に降りてきていない段階だというのは承知しているが、第3段階の新たな価値やサービスの創出が、どういったものになるのかもっと語っていただければと考えるがいかがか。
県A. これまではペーパーレスなど地味な取組が多く、なかなか県民への情報発信が十分ではなかった。今後は第2段階ということで、GIS、メタバース等も増えてきたので、最終的なゴールとして、まずは県民サービスが向上して便利になって、社会全体がDX化していくということについて、しっかりと情報発信に取り組んでいきたい。
質問2⃣
野本Q. 全職員のデジタルスキル向上に関して。勉強ツール等、資格取得に対して何らかの支援はあるか?
県A. 知事のお話もあったITパスポートや、基本情報技術者試験などの資格取得、実践的スキルの習得に対して、民間のeラーニング講座等を無料で受けられる。
また、デジカフェの中でITパスポートの過去問題を配信したり、取得を目指してる人がリアルで集まっての勉強会も実施し、トータルで職員のスキル向上を後押ししている。
質問3⃣
野本Q. デジタルを活用した県民サービスの向上で、電子化の阻害要因として、電子化を阻害する規定が県でも43%ある。これは具体的にはどのようなもので、改善は見込めるのか?
県A. 県が阻害の主体となっているものは、資料にある通り43%あり、直接的には県の要綱や要領などで、対面での状況確認が必要、書類の原本提出が必要などの規定を定めているものが多いためである。
このうち、改善が見込めるものについては、例えば本年6月に、これまで書類の原本提出を求めていた手続を、対面での提出以外の方法を認める規定の改正を行った結果、手続のオンライン化ができた事例がある。
このほかにも対面により聞き取りを行っている手続に関し、他県ではZoom等を使ってる場合があると聞いている。本県でも導入が可能かしっかり検討していきたい。
規定の見直しとあわせて、デジタルツールの活用をどうしたらいいかの両面から阻害要因の解消に努めていく。
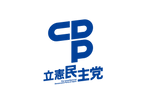


コメント